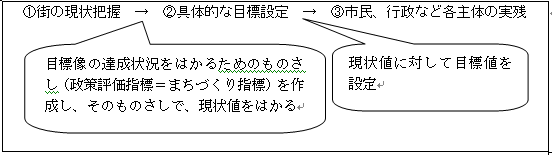ポスターセッション要旨
P1
熱田親憙(関西国際大学)
「メコン川流域の持続可能な開発に当たって」
1.21世紀は水不足の世紀。米国、中国に食糧や工業生産を依存しているが、この依存の構図は崩壊する。日本の安全保障(生存)のため、次の自衛手段が必要。その候補地が水の豊富なメコン川流域。
2.この流域に対する期待は二つある。
①穀物と工業製品の輸入元(日本)としての経済特区の開発
②流域諸国の経済特区としてのメコン川経済圏の形成による経済的発展
3.流域開発に当たっての阻害要因
4.解決を握るメコン川委員会の問題点と解決
P2
伊丹康二(豊中市政研究所)
「豊中市における協働型政策評価の取り組み~円卓会議への情報提供のあり方~」
【研究背景】
豊中市では、「総合的な行政評価システム」の構築に向けて約6年前から取り組んでいる。その構成は、政策・施策評価-優先順位付け-事務事業評価となっている。豊中市では、総合計画に示されている豊中の目標像は行政だけではなく、市民やNPOなど多様な主体による取り組みが不可欠という前提のもと、政策・施策評価を「協働型評価」と位置付けた。その役割を担う組織として平成16年2月に「とよなか未来会議」が発足した。
【とよなか未来会議の役割】
市民、行政、事業者などが豊中市の目標像に向かってまちづくりに取り組むために、
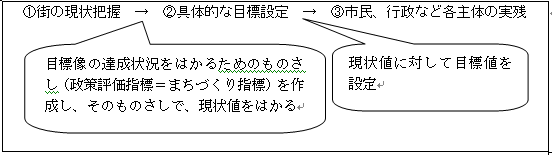
というシナリオを書いている。この①、②の段階が、協働型評価であり、吹き出しの中に書いた具体的な作業を行う組織が「とよなか未来会議」である。
【研究要旨】
多様な立場の参加者が、お互いの情報や価値観を共有し、議論を進めるためには、基礎的な情報の提供が重要である。しかし、提供する情報の内容、提供方法によっては、一部の参加者の発言を制限することにもなりかねない。適切な情報提供とはどのような情報を、どのように提供することが望ましいのか。とよなか未来会議の活動を通して研究を行った。昨年度のポスターセッション、「豊中市における協働型政策評価の取り組み~市民による政策評価指標づくリ~」に引き続き、今年度は、とよなか未来会議のような多様な主体が議論を行う円卓会議(ラウンドテーブル)において、情報提供が重要であること、さらにはその提供方法について十分な配慮が必要であることを示した研究報告を行う。
P3
植田宜裕(シャープ株式会社空調システム事業部国内商品企画部)
「環境対応商品"家庭用生ごみ処理機"の開発プロセス」
環境に関する機運が高まる中、当社は「環境先進企業」として、ECO商品の開発を積極的に行っている。これの取り組みとして、液晶テレビAQUOSを軸とした「省エネ」、太陽光発電システムによる「創エネ」に続く、ごみの排出量抑制に寄与する「生ごみ処理機」を今回の発表テーマとし、
①環境先進企業とした当社のブランド価値を高める
②生ごみに関する情報提供を行い、学生の意識を高めさせる
③マーケット調査分析から商品化までの開発プロセスを紹介
以上の要旨をもとに対応して参ります。
P4
北村直樹(長浜市役所)
「都市観光を振興する個性的景観形成の手法に関する研究~長浜・彦根・近江八幡の三都市の事例調査~」
近年、政府が観光立国を推進する等、観光への期待がますます高まる中、国内観光は低迷を続け、国内観光地においては点的観光から面的観光への旅行者ニーズの変化等への対応に迫られている。そのような状況下において、地方の都市観光地では、歴史的街並みを観光資源とした観光地が成功を収め、それに伴い各地で空間整備への関心が高まっている。その一方で、美しさを目指した規制・誘導による統一的な景観形成は、景観の画一化を招いていると言われ、都市観光地においても大きな課題となっている。そこで当研究では、都市観光を振興するための個性的景観形成手法として、「景観の統一と多様性」と「景観の地域特性」に注目した。そして、歴史的景観整備による観光化の成功事例として長浜・彦根・近江八幡を取り上げ、それら三都市を対象とする事例調査を通して、どのような景観要素に統一性、多様性、地域特性を持たせれば良いのかを考察する。
P5
佐々木正人(株式会社竹中工務店プロジェクト推進本部)・米津寛司(社団法人関西経済連合会都市・文化グループ)・橋岡佳令(竹中工務店プロジェクト推進本部)
「美しい・たおやかな大阪まちづくり研究会~大阪の個性を生かした美しさ向上を目指して~」
【研究会の主旨】
当研究会は平成15年度都市再生委員会活動方針にて「美しい・たおやかな大阪グランドデザイン」の策定を目指して設立された研究会である。設立の背景には平成15年7月に、国土交通省より、「美しい国づくり政策大綱」が発表されたこと、それに続いて景観基本法の制定など、国レベルの景観向上の新しい動きが始まったことがあり、そうした動きを受け、大阪でも景観の見直しと対策の検討を始めることが重要との認識があった。
大阪都心部は、他都市に比べて不法駐車や、あふれる看板など景観面でのマイナスイメージが強く、都心居住や集客観光都市などの推進を滞らせている原因ともなっている。このままでは都市再生はもとより、国内外の都市間競争に大きく立ち遅れることも予想され、早急な改善が望まれる。また、その方法として、行政のみならず、都心部の企業や市民が一体となったタウンマネジメントへの期待が高まっている。そこで大阪の都心部を対象に景観の調査研究を行い、行政、企業活動、市民生活への提案を含めた美しい大阪づくりに貢献し、住みたい・訪れたい大阪の実現を目的として活動を開始した(事務局を関西経済連合会・都市文化グループと、竹中工務店・プロジェクト推進本部が務めたものです)。
【活動概要】
①大阪市内に働くビジネスパーソンを対象に、「大阪の美しさ向上に関するアンケート」を実施。都心部の10エリアを取り上げ、現状認識や美しさ向上策などについて質問した。調査はインターネットにより、約1600回答を得た。
②それら主要エリアをフィールド調査し、実態の把握と分析を行った。
③アンケート調査、フィールド調査の結果をタウンマネジメント団体や行政などにフィードバックするとともに、ヒヤリングを行い、美しさ向上のための方策を検討した。
④以上の成果をもとに10項目からなる提言としてまとめた。
【提言内容】
提言の内容は下記のとおり。
①大阪では、エリアごとの特性を踏まえた美しさ向上策を実行しよう。
②そのためにまちづくりや、街の維持管理・運営を、エリア単位のタウンマネジメントへと再編していこう。
③地元組織をタウンマネジメント団体として認定する制度を設け、委託可能な維持管理や運営は認定団体に委託しよう。
④タウンマネジメント団体の横の連携を図るプラットホームを設置し、景観向上活動の相乗効果を高めよう。
⑤大阪の「顔」となる大型ターミナル周辺の美しさ向上を目指そう。
⑥道路・公園などの計画・整備は、完成後のタウンマネジメントを含めて検討・推進しよう。
⑦事業主はその活動のなかで、大阪の美しさの阻害要因となっているものを見直し、美しさに貢献するよう改善していこう。
⑧大阪の美しさ向上に資する業務改善を行なった事業主を認定・表彰する制度を整備しよう。
⑨公園・河川・歩道上の美しくない看板・施設類は見直してほしい。
⑩市民への景観向上PRと、子供を中心に景観教育に取り組んでほしい。
P6
八頭司彰久(滋賀大学経済学研究科博士後期課程)
「損害保険会社の社会貢献~環境商品を中心として~」
損害保険会社は、地域社会、地域経済、生活経済に対して、環境商品を中心として貢献をしている。このタイトルでは、損害保険会社の環境商品の開発の実例に基づいて、社会貢献の現状と問題点について考察する。
P7
井口昌哉(総合政策学部4年)・石田地文・奥律子
「外国人労働者の現状と私たちの意識」
今回私たちはアジア系外国人労働者に焦点をあて、プレゼンをしたいと思う。フィリピンとFTAを締結したことや日本の労働人口減少によって、看護師および介護士の流入が増加してくると考えられる。そんな中、現在彼らを受け入れている現状はどうなのか。そして私たちが現在抱いている彼らに対するイメージはどうなっているのか。またこれから受け入れるにあたって何が重要になってくるのかを探っていきたいと思う。
P8
植田博之(総合政策研究科M2)
「建築物総合環境性能評価システム(CASBEE)を活用した建築物の環境価値に関する調査研究」
【背景】
持続可能社会の実現に向けた取組みのひとつとして建築分野では、1980年代よりイギリスのBREEMや北米のLEED、国際的なGB Toolなど、建築物の環境性能に関する評価手法が多く開発されてきたが、我が国においても、国土交通省支援のもと産官学共同プロジェクトとして建築物総合環境性能評価システム(CASBEE)を開発、昨年頃より普及・推進が本格化してきている。
現在、そのような流れを受けて3大都市圏の各自治体では、①建築物着工時に建築主(設計者)がCASBEEを使用して計画建物の総合的環境性能評価を実施し、②その結果を記載した計画書を自治体に届出を行い、③自治体はホームページ等でその計画書の概要を広く市民に公表する制度(制度名称:建築物環境配慮制度、建築物総合環境評価制度等)もスタートしている。
CASBEEは、建築物の総合的な環境性能について3分野10領域、約50の評価項目による"建築物の環境品質・性能(Q)"と、3領域12分野、約20の評価項目による "建築物の環境負荷低減性(L)"の各スコア(レベル1~5の得点)から算出される環境性能効率(BEE)により5ランクにラベリングされるが、評価が行なわれた建築物のQ及びLの各領域のスコアからは、建築物を構成する多様な環境性能の"質"を分析することもできる。
【修士論文の概要】
修士論文では、CASBEEを "環境に配慮した建築物の誘導政策"を立案するための基礎的なデータの収集ツール、そして建築物のつくり手と使い手のコミュニケーション・ツールに位置付け、年間着工床面積の最も多い集合住宅を対象に以下の研究を行なう予定である。
①つくり手における環境配慮設計の性向分析:名古屋市及び大阪市、横浜市の同制度により届出・公表された建築物の環境性能を統計的に分析することで、つくり手(建築主・設計者等)の環境配慮設計の性向を明らかにする。
②Q及びLの各環境性能(属性)に対する使い手の価値の評価:集合住宅の環境性能に関するアンケート調査及びコンジョイント分析により、CASBEEを構成するQ及びLの各評価項目(属性)に対する使い手の支払意志額の評価を行なう
③建築物に対する公共的な環境価値のあり方の考察:①により明らかになる性向を、各種法規や様々な制約条件の元でのつくり手による「社会的な環境価値」、②により明らかとなる各環境性能(属性)に対する使い手の価値の評価を「個人的な環境価値」と考え、双方の立場が共有できうる「公共的な環境価値」のあり方を考察する。
【ポスターセッションでの発表内容(案)】
ポスターセッションでは、修士論文の中間的な報告として以下の内容を発表する予定である。
①建築物総合環境性能評価システム(CASBEE)の概要
②名古屋市及び大阪市における建築物環境性能評価制度の現状
③名古屋市及び大阪市のCASBEE公表データを用いたつくり手(建築主・設計者)の環境配慮設計の性向分析
④集合住宅の環境性能に関するアンケート調査やコンジョイント分析の計画概要(案)
P9
FSTサイバー会議(代表:中野幸紀総合政策学部教授)
「学生が描くイノベーションシナリオ~FSTサイバー会議への誘い~」
地球環境、都市問題、途上国問題などの解決に「イノベーション」が重要な役割をはたす。どのような科学技術シーズによっていつごろまでにどのようなかたちで社会的なイノベーションが進行・展開していくこととなるのか。文科省が提示する50のシーズ課題技術分野ごとに、全国の学生からの自由な意見と展望をシナリオ電子会議(FSTサイバー会議)に集約し、学生議長がそれぞれの課題分野ごとにひとつひとつのイノベーションシナリオに編み上げていくことが可能かどうか。昨年度のKSC版電子会議の結果と今夏に予定している全国版(拡大型)電子会議の準備状況を中間報告する。
P10
加賀田和弘(総合政策研究科D3)
「環境対策と企業業績」
本研究では、多くの企業が環境対策に積極的に取り組むことの重要性を認識し、それを経営戦略上の一環として意識するきっかけとなった京都会議開催の97年からすでに7年が経過したことを踏まえて、京都会議開催以降のわが国企業の環境対策と財務業績との関係について考察している。特に、ISO14001認定取得、環境告書や環境会計の導入など、具体的な取り組みが実際に多くの企業で行われ始めた2000年から2004年までの最近5年間の、わが国企業(製造業)における環境対策と財務業績との関係について定量的な分析を試みている。
本研究におけるResearch Questionは以下の4つである。
①環境対策に力を入れている企業と、そうでない企業との間に差があるか?
②環境対策に力を入れている企業は、そうでない企業に比べて、その後業績が良くなっているのか? あるいは、環境対策に力を入れていない企業は、力を入れている企業に比べて、その後業績が悪くなっているのか?
③過去の業績によって、環境対策に力を入れる企業と、あまり力を入れない企業の間に違いが見られるか?
④業績は良くないが、環境対策に力を入れている企業、および業績は良いが、環境対策に力を入れていない企業は、その後業績がどのようになったか?
これらを基に仮説を設定し、分析を行った。
P11
孫剣氷(総合政策研究科D1)
「地域社会に開かれた歴史的庭園の再生~中国蘇州市旧市街にある庭園住宅を事例に~」
蘇州市の旧市街には、街区を基本単位とする伝統的市街地が形成されている。現在でも人々が生活する居住区で、一つの地域社会が形成されている。蘇州の庭園住宅の多くもこれらの地域に立地している。庭園住宅とは、自然の趣を享受できる庭園部分と、居住機能を果たす住宅部分から構成されている邸宅のことである。中国ではこのような邸宅を「園林」と呼んでいる。庭園住宅は、旧市街の歴史的環境の産物であるとともに、近代における用途変化や文化財としての見直しなどによって、その機能を変化させてきた。その結果、現在、保全に限界が認められる。地域の物的空間と地域社会の特徴をふまえて、現代都市において庭園住宅に新たな機能を付け加え、再生することを提案する。
P12
月岡悠(総合政策研究科修士課程修了)・原好江(総合政策学部4年)
「社会的側面からみた在日ブラジル人におけるHIV/AIDS予防対策」
日本においてHIV/AIDS予防対策の取り組みは遅れている。その中でも、対策をとるべきターゲットとして在日外国人の場合、さらなる困難があるのではないか。今回私たちはそれを調査します。
P13
波多野栄(総合政策学部4年)
「グループウェアの活用における情報セキュリティの向上」
実際に開発をしたスケジュール管理システムを具体例に、グループウェアの情報セキュリティの向上のためにどのような工夫が出来るかを発表します。発表内容は情報セキュリティの3大要素といわれている機密性、完全性、可用性の確保に分類をします。
機密性の確保としては、グループウェアならではの、ユーザー権限の調整について発表をする予定です。スケジュール管理システムの構築の際に、機密性と利便性をどのように両立させたかをポスターに掲載する予定です。
完全性と可用性の確保に関しては、グループウェアが稼動しているサーバーを攻撃から守る方法や、システムの信頼性を向上させる方法を発表します。具体的には、データのバックアップやソフトウェアの更新を、ユーザーにとって少ない負担で行うために工夫した点をポスターに掲載することになると思います。
結論として、グループウェアという複数人で活用するシステムでは、ユーザーを個人個人として捉えずに、ユーザー同士の繋がりが一つのネットワークを作っていると捉える必要があるといったことを述べる予定です。
P14
堀内文普(総合政策学部3年)・内山雄介
「JR奈良駅前開発プロジェクト~新しい観光商業空間の提案~」
JR奈良駅の西側及び東側には広大な空き地がある。現在は奈良市主導の下、老人ホームなどの建設が始まっている。しかし、私はこの立地と環境を活かし、奈良を活性化するために、これとは違う新しい観光商業施設を建設することを考えた。
今回のプロジェクトのターゲットは、地域住民と観光客(特に中高年と外国人)に設定する。ターゲットが幅広く思えるかもしれないが、これが成功すれば今までにない活気ある空間を創造することができるであろう。次に集客を図るために、観光客や地域住民のニーズを調査した。その結果、両者ともに共通した不満が食事をするところが少ない、閉店時間が早いということであった。さらに、観光客の不満としては、交通が不便、ホテルが少ない、案内が不十分、などが挙げられた。
具体的な政策案は主に三つある。一つ目はホテルの建設である。奈良への観光客は韓国人をはじめ日本人でも比較的裕福な観光客が多い。しかし、奈良には質の高いホテルが非常に少なく、そのため京都市内に宿泊する人がかなり多い。このことを踏まえて、今回駅西側の閑静な雰囲気を利用して一流ホテルを誘致する。さらに特徴を出すために、宮大工の産業とタイアップし、近代的ホテル建築の中にも奈良らしい古風な趣のある空間を創造する。
二つ日の政策は、レストラン街を備えたショッピングモールの建設である。これは駅東側のにぎやかなエリアに建設する。そしてこの建物の前には広場を作り、地域住民や観光客など奈良を訪れた全ての人がくつろげる憩いの場にする。そして休日にはさまざまなイベントを企画し、さらに活気のある空間作りを行う。そして、レストラン街は深夜まで営業し、奈良の特色を生かした店を中心に出店する(柿の葉寿司を店内で食べることのできる店など)。
三つ日の政策は、新しい観光案内所の設置である。現在JR奈良駅内に観光案内所があり、奈良市では一番の利用者数がある。しかし、現在の観光案内所はフロアが狭く設備も充実しておらず、外国人利用者に対するサービスがよくない。よって、この観光案内所を当該地に移転することにより、より快適な空間でよりよいサービスを受けられるようにする。具体的には、外国語パンフレット、電子式観光案内図、小型ナビゲーションシステムの貸し出し、外国語対応のインターネットサービスなどが考えられる。
以上が主な政策案である.今後の課題としては、深夜の治安維持の問題、広告、宣伝方法の検討、近隣ホテルとの競争、協力などが挙げられる。これらのことを踏まえて、すばらしい奈良の新しい観光スポット、そして地域住民にとってのすばらしい娯楽施設になればと考えている。
P15
前田彬宏(総合政策学部2年)
「目標設定・目標達成を支援する場を広め、学生の意識を変える政策提案」
【問題意識】
現在日本国内においては教育の危機、学生の危機が盛んに叫ばれている。フリーター・ニートの増加がマスコミでも取り上げられ、就職しても3年以内に退職してしまうケースが大卒で3割以上というデータもある。若年世代でも不登校のケースが増え、さらに「やりたいことが見つからない」「将来に希望が持てない」と言った悩みも増加しているそうだ。これらは学生である我々自身が肌で感じていることでもある。しかし一方でやる気に満ち溢れ、様々な活動を行いながら学生生活を送っている者もある。そして、IT化とグローバル化の波が押し寄せ、市場競争力のある者とない者の差が歴然としてきている。この現状から未来を予測していくと、現在のような国民総中流階級といった状態は崩れ、次第に所得格差、つまり貧富の差が大きくなることが想像できる。所得格差が開くことで、治安が悪化し、社会保障による財政の圧迫が起き、社会が不安定となり、また次世代における教育の質にも影響を及ぼし、より一層の所得格差が生まれることが予想される。このような状況になる兆候は既に表れ始めており、我々は早急に対策を講じなければならない。このような問題意識から、国民の所得格差が開くことを未然に防ぐための政策を、学生の視点から今回は発表する。
【問題分析】
所得格差が起こる要因は各自の能力差のみではなく、個人の目的意識の差にあると考えられる。それは、「成長しようという意欲があるかないか」とも言い換えられ、この意識の差によって、数十年というスパンで見た際に、各自の能力に多大な影響を及ぼすと言える。特に自由な時間の量が格段に多い学生時代における人格形成、能力形成は後の人生において重要な位置を占める。つまり所得格差の拡大を未然に防ぐためには、成長しようという意識付けを若者世代に植え付ける必要がある。彼等が成長しようという意欲を持たない要因は、裕福な社会環境、受動的になる教育方法、バブル崩壊後の社会の変化、周囲の影響、などである.
【政策提案】
さて、それでは若者が成長しようとする意欲をいかにもたせるかだが、先に述べた要因を取り除くことは、一学生ができる範囲とは言い難い。しかしながら、成長しようと思う新たな要因や、そのための「場」を作り出すことは可能である。モチベーションというものは他人から言われて上がるものではなく、自発的に上がるものである。私が今回提案するのは、「目標設定・目標達成支援の場の普及」である。各自が自分のできる範囲の目標を設定し、それを達成することを目的とした場を設け、集団で行うことで目標を「やり切る」習慣を身につけ、受身ではなく主体的に行動し、達成感を味わわせる。このような場を日本中に草の根的に設けることで、日本人全体としてのモチベーションが上がることが期待される。現在企業においても各自に目標設定を委ねる手法は広まりつつあり、深刻な教育問題を抱える現在の日本において、非常に有効な手段であると言える。
P16
阪口愛子(総合政策学部2年)・黒木美紗(同3年)・真野絵里加・達城亜未
「マレーシアへ行きませんか?」
昨年の夏に私たちが企画し、実施したマレーシアホームステイツアーの報告をします。参加者の皆様から大変好評を受け、今年の夏も実施することになりました。マレーシア文化やエコツーリズム、美しい自然、きらめく海、現地の人々との触れ合い、豊富でおいしいトロピカルフルーツ、などなど....皆さんにもっとマレーシアのことについて知ってもらいたい。私たちと一緒にマレーシアホームステイをしませんか?
P17
相馬めぐみ(関西学院大学商学部2年)・村田実(総合政策学部2年)・岡田恵・岩村和彦(社会学部2年)
「国際インターンシップをビジネス・ツールに」
P18
赤尾直子(総合政策学部3年)・松田祐介・井川亮太・池永知嗣・太田慎吾・紙谷昌典・桑野陽介・寺田浩平・松宮悠一・村田実・綿谷翔吾
「グローバルリスクマネジメント On the Web」
今世界では、人口爆発、環境破壊、経済格差、戦争、紛争といった危機的状況が同時に存在しており、環境、及び資源リスクを考え世界各国が協調して経済活動を誘導することが求められています。私達は、この世界規模の危機的状況をどのように生き抜くか、また解決するかについて、主に水、食料、そしてエネルギーに焦点を当てて、グローバルな視点から調査を進めていきます。具体的に、ゼミ生全員がそれぞれ違う国を担当し、担当国の人口増加に伴う水、食料、エネルギー要素の推移を統計データに基づいて作成し、それらの情報を実験室のサーバー上の領域に掲載する予定です。そして、どのような問題が何時、どこで、どのくらいの規模で発生するかを定量的に把握し、問題提起・解決方法を最終的に示したいと思っています(http://210.81.218.161/GRISK/world01.html)。
P19
曽根田香(総合政策学部4年)・長谷川真紀・後藤美香
「杉材をもっと使おう!! ~日本の林業再生にむけて~」
今日本の林業は壊滅的な状況を迎えています。戦後植林された杉の伐採時期が来ており、木材資源は豊富にあるにもかかわらず、海外から輸入される安い木材に押され、国産木材の需要は落ち込む一方です。今では伐採するだけでも赤字が発生する状態で、山林は間引きなどの手入れもされず、放置され、荒廃が進んでいます。現在ある国産材は、日本国内における木材需要を持続可能的にまかなえるだけの量があります。こうした状況を改善するための方策について以下の流れで映像を使いながら報告を行います。
①林業の現状把握
②製材の流れ
③杉製品の販売戦略
④そのための具体的なアクションプラン例(http://wwv.kyusou.net/table.htm1)
⑤エコオフィス大賞に関連する情報提供
なお、42インチのプラズマディスプレイ+音響器具、透明のアクリルボードを使ったプレゼンテーションをおこなう準備を進めています。
各種活動情宣
以下の総合政策学部関連団体が広報・情宣ブースを設ける予定です。是非、御照覧下さい。
1.総合政策学部リサーチ・フェア実行委員会
2.総合政策学部キャンパス・ミーティング2005実行委員会