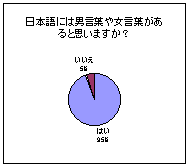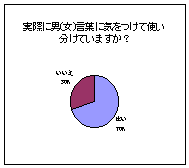陣内ゼミプレゼンテーションまとめ
‐日本語の男女差‐
‐構成員(50音順)‐
岡田 英理 呉 迪 西澤 弘典 宮前 実幸
l
研究テーマ
|
わたしたちのグループは、『日本語を学ぶ外国人にとっての男女差』に焦点を絞り、そこから、外国人を迎える我々日本人の持つ、男女差に対する意識について考えた。 |
l
日本語の辞書・教科書に見られる男女差
‐辞書の用例の中にみられる男女差
|
では、実際に辞書の中に見られた用例を見てみよう。
|
移る |
彼女は気が移りやすい |
|
努め |
彼女は夫の親によく努めている |
|
慎み深く |
彼女は夫の後ろに慎み深くすわって、ほとんど口をきかなかった |
|
最大 |
彼女は結婚によって最大の幸福をつかんだ |
|
気持ち |
彼女は気持ちが変わって、ほかの人と結婚した |
|
道具 |
女性はいつも化粧の道具を離さない |
|
捨てる |
妻子を捨てて逃げる |
|
支配 |
女性は感情に左右されることが多い |
|
幸福な |
いい奥さんを持って、幸福な生活ですね |
|
機嫌 |
あの奥さんは夫の機嫌をとるのがうまい |
|
助ける |
あの奥さんはご主人の研究を助けて、ついに完成させました |
|
棒に振る |
あの人のお父さんは女の人のために地位を棒に振った |
|
内職 |
家計を助けるために女の人などが家出暇をみてする仕事 |
|
つつしむ |
調子に乗りすぎた行動をして、身の破滅を招いたりすることがないように、自らを戒める。酒(女・口)をつつしむ |
過去の調査によれば、辞書の用例に出てくる男女の比率は、男性が79、女性が24と、
圧倒的に男性の出てくるケースが多かったという。
さらに、『い』の部分ではその割合はなんと、100:27になっていたという。
私たちが調べたケースでは、反対に男女ともに例文の中に使われているケースが少なかったように感じた。
これは男女差別につながることを過剰に避けようとした結果なのかもしれない。
‐教科書の中では‐
|
文章には、『結婚して会社を辞めた』のように『結婚』にまつわるものや、『家内』を使った例文がたびたび出てくるとある。呉君の学んだ教科書にも確かに、男らしさ、女らしさについて書かれた文章が見られ、同時に、『家内』という日常ではなかなか耳にしない単語を知っていたことからも、日本語学習の過程で学んでいた事実が予想出来る。そして、このような言葉を通して、日本人女性=慎ましいというステレオタイプが生まれているという可能性も否定できない。 |
‐男口調・女口調‐
|
上で見たパターンは、単語レベルでの男女差である。では、ある種日本語特有のものであるとも言える、男女の口調の違いは、外国人にとってどのように捉えられているのだろう。呉君は以前バイト先で、言葉遣いが女言葉であると指摘された体験があるという。EC講師のデイビッド・ベグラー氏も、ほとんどの外国人は、女口調の日本語を身につけてしまうと語っていた。残念ながら、詳しく話を聞くことができなかったため、その原因などは不明だが、外国人は、口調の違いをどのくらい意識して日本語を学んでいるのかアンケート調査を行ってみた。結果は以下のとおりである。 |
||
このように、ほとんどの外国人が日本語には男女口調があると認識している。しかし、それを実際に意識して使っている割合は、7割程度にとどまっている。この理由としてもっとも多いのは、そこまで違いを意識して話す余裕がない、というものであった。そもそも、言葉というものは、生活を通して身に付く要素が大きい。男女言葉があることを認識した上で、日本語を身につけていくのであれば、長い目で見た場合、それほど重大な問題にはならないのかもしれない。呉君のように指摘されるようなケースでも、そもそもコミュニケーションを取るということを一番の目的としている、外国人の語学学習において、口調などは、後から補われればよいものではないだろうか。これは、敬語や丁寧語など、シチュエーションによって変わる日本語の用法の学習などとも似ているところがある。 |
l
そもそも、男女平等とは
言葉の男女差から生まれる偏見などについて考えていくうちに、私たちは、
そもそも男女平等とはどのような概念なのかという疑問にぶつかった。
そこで、現在国内での、男女平等の捉えられ方を調べ、そこからグループとして
定義をしてみることにした。
−男女共同参画社会基本法の大義−
|
能力のある女性が社会でその能力を男性と同等に発揮できる社会を実現しようというもの |
ところが・・男女平等を意識するあまり、各地で様々なトラブルが・・・
|
Ø 県立高校の男女共学化 |
|
Ø 男女混合名簿 |
|
Ø 男女混合騎馬戦 |
|
Ø 小学校高学年の校外宿泊学習で、男女を同室に宿泊させた |
|
Ø 高校で、体操服に着替える時、男女が同じ教室で一緒に着替えていた |
|
Ø 鯉のぼりやひな祭りを否定的に捕らえるパンフレット |
|
Ø 大宰府舘のトイレ表示が、黒で統一されて混乱が起きる |
|
Ø 文部省が、財団法人日本女性学習財団に作成させたパンフレットに・・・ 女の子に「優しい愛らしい名前」赤のランドセル暖色系の服装・お人形・ひな祭り男の子に「スケールの大きい強い名前をつけてはいけない」黒のランドセルや寒色系の服装ミニカーやサッカーボールのプレゼント・鯉のぼり・5月人形はいけないとの記載があった。 |
‐男女平等を唱える人々の考え方‐
フェミニストの主張は、男らしさ、女らしさは、社会的、文化的につくられるものであり、
男女には生物的な本質はほとんどないというものである。これは、ジェン・マネーの
「新生児は、性心理が白紙の状態で生まれる」という説を論拠としたものであるが、
現在科学的に否定は完全にされている。
つまり、現在では、身体面においても、心理面においても、生まれた時に既に違いはあって
当然である、というのが現在の定説なのである。
‐わたしたちの考え‐
もっとも重要なことは、このような個人個人の能力を固定観念によって決め付けること
こそが、いわゆる固定観念を生み、男女差別の現況になるということである。
男女が何かすること(例えば、男の子が人形で遊ぶことも、女の子が人形で
遊ぶこと)を、ともに否定するのではなく、これまで、当たり前に考えられて
きたことも、これまで否定的に考えられてきたことも、自由な選択肢として肯定
していくことが男女平等のあるべき姿なのではないだろうか。
そして、個人が自由に選択を出来る中で、それぞれの能力が問われていくべきなのである。
女性だからといって、全員力が弱いと決め付けると、男は文字通り痛い目に遭うかもしれない。
l
総括
|
今回、日本語の男女差を考えて、やはり外国人に日本語を教えるわたしたち一人一人が、もう一度、男女平等というものを考える必要性を感じた。言葉というものは文化であり、裏を返せば、文化が言葉を作るとも言えるからである。 ただし、男女の口調の違いに関しては、日本語文化の一つの特徴として捉え、教育の現場においても、特別強調していくべきものではないと考える。ある種、日本語の売りのようにして教育現場で教えるのではなく、もし、違いの存在を伝えるのであれば、そのようなことについて、日本人の中にある考え方、また、具体的にどのようなシチュエーションで用いられるべきものなのかなどを捕捉し、生活の中で、より円滑に日本語を身につけていけることを最優先に考えられていかなければならない。 それとは反対に、今回調査した、単語レベルでの男女差意識というものは、まさに、言語政策というよりも、まず意識レベルで見直すべき問題である。男女平等というものは、上から押し付けていくものではないのだが、それ以上に、男女差に関わる偏見を教育によって押し付けていくようなことは避けなければならない。これまで、無意識に上の例で見たような言葉が示されてきたのであれば尚更、教育者は意識を高め、注意深くなる必要がある。言葉の問題、また、男女差意識といった考え方の問題を、大きく文化と捉えれば、これらがお上によって押し付けられる性質のものではないと、よりはっきりと断言することもできると、私たちは考える。 |