|
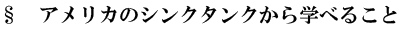
先ほど述べましたとおり、アメリカには数多く多様なシンクタンクが存在します。日本には、やっとシンクタンクの必要性が認識され始めた段階にあります。それゆえ、アメリカは、議員と研究委員が頻繁に勉強会などで議論ができる場所が多く、1日に100もの議論を行うときもあるのです。一方で、日本では議員・職員などは皆忙しく、勉強会などする機会も稀であります。この理由を簡単に説明しますと、アメリカと日本の間に文化的な違いがあります。ブラウンバック的なでいろいろな分野のさまざまな地位にいる人が参加できるということであり、日本のいわゆる「儀式的な」会議や勉強会ではないということです。
そこで、21世紀の政策提言システムは以下のようなものが求められます。
|