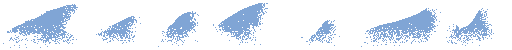
1.GDPという指標
1-4. GDP
指標の限界−福祉との関係において−戦後において人々は物質的なものを必然的な状態から追求し,それを支える制度が構築され,絶対的貧困は免れるようになったのであるが,一方で相対的な不平等は拡大していった.絶対的な貧困から脱し相対的不平等が目に見えるようになった現在の
Epochにおいて,人々は人間主義的なものを要求するようになってきた.それまで,社会全体を支える政策は展開されても個々人の状態を支持するような政策は実施されなかった.それゆえ,個人の状態を支持するものが要求され,その集大成として誕生したのが福祉社会,福祉国家という概念であった.言い換えれば,
GDPという数量的な概念からそれを超越する経済的次元の問題を取り扱う必要に迫られることになった.所得と福祉の密接かつ実証的な関係はもはや完全に適用されるものではなくなり,反対にその関係に疑問をもつに至った.しかしながら,ここで注意したいことは
GDPが指標そのものとして役に立たないのではなく,本来,福祉の指標として適用することに問題があるという点である.いずれにしても,GDPは経済的福祉を測る規定因の一つであることに変わりはないのであるが,すべてを示す指標と考えると無理が生じる.GDPの拡大を目指す目標,いわゆる経済活動の目標として福祉や欲求の充足が存在するのであり,その目標を達成する物質的手段として財やサービスが,経済的資源から生産される.しかし,それだけでは福祉や欲求の充足は満たされない.つまり,GDPだけでは福祉を完全に表現できないことが,GDPが福祉の指標として不適切である根拠となる.以下にその概念図を示した.
図2: GDPと福祉の関係
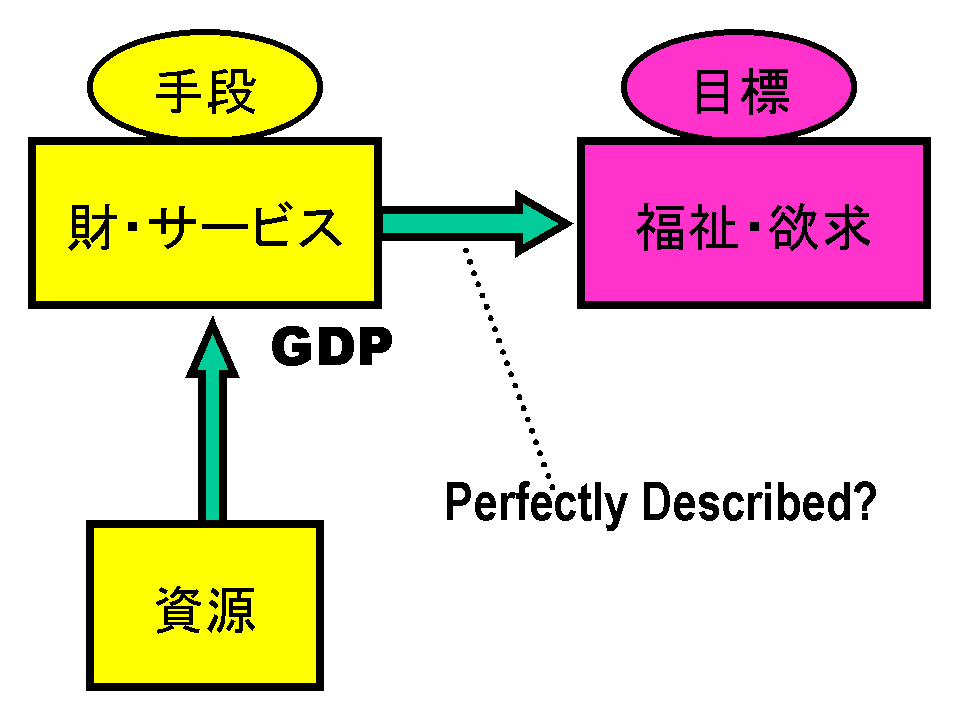
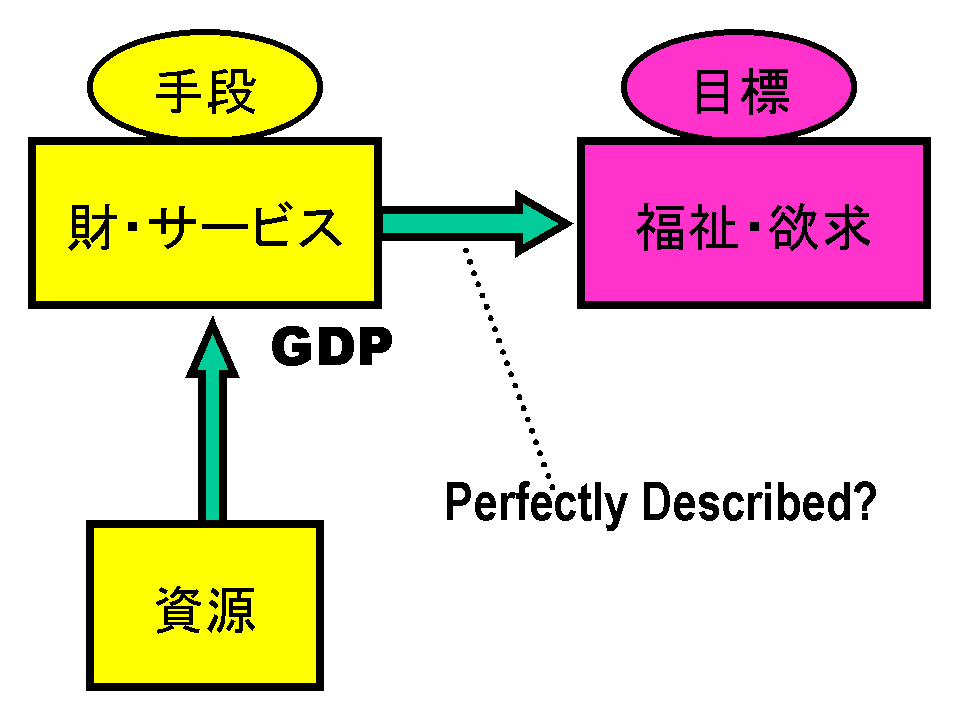
[福祉経済の理論pp.39-40を参考に作成]
ここで少し具体的に
GDPと福祉の関連性への疑問を展開したい.例えば,環境問題や公害問題でしばしば話題になるのが外部性であり,市場機構で処理されないことによって引き起こされる問題である.GDPにはカウントされないが,福祉への影響は明らかである.つまり,所得(GDP)の大きさで福祉の大きさを測ることは必ずしも正しくないということである.