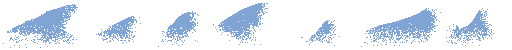
2.潜在能力という指標
−人間の豊かさを問うアプローチ−
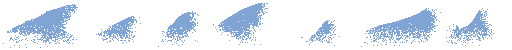
2-1.潜在能力と機能
ここまでは
GDP指標,いわゆる経済学でいう財の量で測る富裕アプローチを取り扱った.次に,この章で扱う潜在能力アプローチの概念を以下に記したい.まず,このアプローチでは潜在能力と機能という二つのキーワードがある.機能とは,財の所有に基づいて個人が達成することのできる多様な活動の基礎となる自立的な生き方・在り方(doing, being)のことであり,例えば,健康であること,早すぎる死を避けること,幸せであること,自尊の念をもつこと,コミュニティの生活に参加することなどが挙げられる.
つまり,財の特性のみでは人々の福祉は測れないとしている.なぜなら,財の特性が分かっていてもその特性を活かせるかどうかはその個人に依存しているからである.例えば,車という財において,車を獲得してもその個人が身体的もしくは精神的に障害があれば,それらの特性を活用できず,その特性を享受することにならない.
したがって,同じ量の基本財を供給されたとしても,特別のニーズをもつ人々(障害者,高齢者,疾病者)はより不遇な境遇におかれる可能性がある.その格差は,彼らが責任をもつことのできる要因に起因するものではないので,もう一歩踏み込んで「人が何をできるか」,つまりその人が実現可能としている機能についてまで考察しなければならない.
また,潜在能力とは,諸財の有する特性を個々人の財(特性)利用能力・資源で変換することによって実際に達成可能であるような諸機能の集合を指すものであり,またその諸機能を個人が自己の主体的意思に基づいて選択する際,外的に妨害されないこと,つまり諸機能の選択可能集合であること・福祉的自由(
well-being freedom)や選択の積極的能力(the positive ability to choose)があることが前提となる.つまり,その財の消費者の機能にまで注目することによって人の福祉に関する判断の情報的基礎を求めようとするのが潜在能力アプローチである.