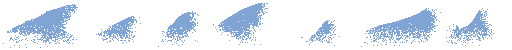
2.潜在能力という指標
−人間の豊かさを問うアプローチ−
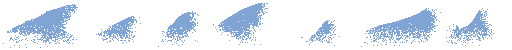
2-6.潜在能力を特定する機能リスト
また,この潜在能力アプローチを実践的に活用しようとするならば,潜在能力を特定する機能のリストが必要となる.機能のリストは生き方や在り方の指標であり,人々の福祉を捉える上で必要不可欠であるのだが,実践的に活用するためには,そのリストの内容について人々の広範な同意が成立していなければならない.その試みを(
図表
2-4 特定の機能に関する5ヶ国のデータの比較6)|
国 |
一人当り GNP($) |
平均寿命(年) |
幼児死亡率 (1000人当り) |
児童死亡率 (1000人当り) |
大人識字率(%) |
高等教育率(%) |
|
インド |
260 |
55 |
94 |
11 |
36 |
8 |
|
中国 |
310 |
67 |
67 |
7 |
69 |
1 |
|
スリランカ |
320 |
69 |
32 |
3 |
85 |
3 |
|
ブラジル |
2,240 |
64 |
73 |
8 |
76 |
12 |
|
メキシコ |
2,270 |
65 |
53 |
4 |
83 |
15 |
[(Sen,1985).引用は(鈴村訳,1988)p.98]
上の図表
2-4は,Senが潜在能力の国家間比較をしようと作成したものである.Senはこれらの項目をもとに比較を試みた.しかしながらここまでの議論の展開では,機能は人の生き方・在り方を指していたのであるが,この上の6項目だけでそれを完全に表しているとは到底言えないし,Senもそれを承知している.その理由を次のように述べている;信頼できるデータが限られているため,潜在能力を拡大し機能を高めるとうい分やにおいてさまざまな国の実績を幅広く比較することは容易でない.この分野のデータが,例えば
それでも,上の図表
2-4からも利用することは可能であり,特にここからは生死や教育に関する潜在能力が読み取れる.例えば,一人当りGNPに関するとインド・スリランカ・中国はだいたい同レベルであり,同様にブラジルとメキシコも同レベルであり,二つのグループに差がみられ違うグループとみなせる.一方,平均余命・幼児死亡率・児童死亡率などでみると,インド一国だけが飛び抜けて遅れており,残り4ヶ国は同レベルのグループに属すると捉えることが可能である.中でも,スリランカは優れているとみなすことができる.つまり,重要な潜在能力である「長生きすること」に関してはインドが劣っている.また,スリランカと中国のそれは一人当りGNPで言えば上のレベルのブラジルやメキシコのグループに属するのである.| 6) 図表2-4の数値はWorld Development Report (WDR) 1984によるものであり,「高等教育率」だけにおいてはWDR 1983によるものである.すべて1982年におけるデータである. |