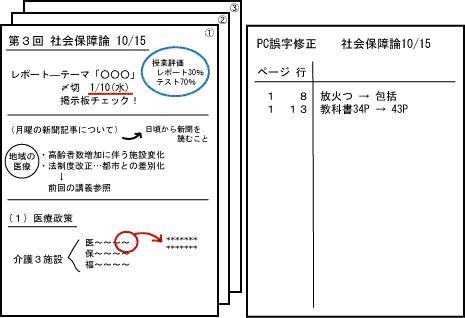
| ◆手書きサポーターが準備するもの | |
| ペン | 太めの黒ペンか3色ボールペン等。シャーペンは避ける |
| 裏紙(20枚程度) | 授業によって必要枚数が違うので、多めに持っていく |
| ◆手書きサポーターがするべきことは3つ | ||
|
|
講義内容を分かりやすく |
●講義内容をまとめて書く ●内容に補足を加える ●図やグラフなどを写す |
|
|
PCノートテイクをフォローする |
●PCの誤字脱字を修正する ●PCで省略された内容を補足 ●利用学生が分からない部分を説明する |
| 3 | 授業をリアルタイムに伝える |
●教員の指示をすばやく伝える ●説明している箇所を指差す ●教員が読み上げている箇所を指でなぞる |
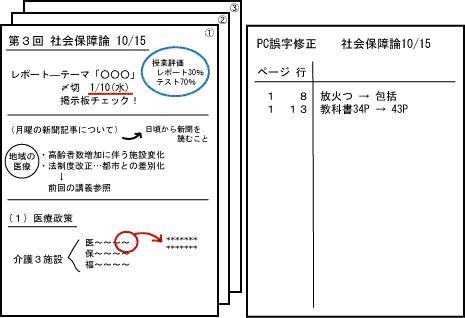
| 1 | 利用者がノートを見やすい位置に座る(自分が右利きなら、利用者の右に座る) |
| 2 | ノートの1枚目に講義名と日付を書き、毎ページの右肩に番号をふる |
| 3 |
文字は大きく、きれいに書く |
| 4 | 文章で書かずに、箇条書きにしてまとめる |
| 5 | 矢印や丸などを使い、関連事項を分かりやすくする |
| 6 | PCの誤字脱字訂正は、別の紙に書く |
| 7 | 教授が強調した部分は、赤ペンで下線を引くなどして、情報を追加する |
| 8 | 黒板に書かれたことはノートにも書く |
| 9 | 授業で使う図・グラフ・表などはノートに写し、講義に沿った説明を書き足す |
| 10 | PC任せにしない。PCが授業の内容を充分フォローしていても「より詳しく、より分かりやすく」を心がける |
| 1 | 講義のみ | PCの内容を箇条書きでフォローする。講義内容の全体図を把握し、簡潔にまとめて伝える |
| 2 | レジュメがある場合 | レジュメと授業の進行度を合わせることを心がける。簡単な説明や関連する用語を書き込む |
| 3 | パワーポイント | 用語や図を見逃さないようにする。コピーがある場合は、空欄に講義の内容を補足する |
| 4 | 資料や記事を使う | 授業のどの箇所の関連記事なのかをメモする。読み上げる場合は、そこを指でなぞる |
→ 手書きサポーターーが主役になって、利用者に授業内容を伝える。
授業中に突然PCの電源が落ちたり、日本語の入力がうまくいかなくなったりする場合がある。そんな時は、手書きサポーターがPCの代役を務め、授業内容を利用者に伝えること。
PCが動かなくなっても授業は止まらない。PCの復旧はPCノートテイカー2人に任せ、筆記サポーターが授業内容をフォローすること。