|
|
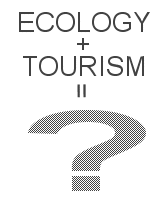 エコツーリズムの定義 エコツーリズムの定義それではエコツーリズムとはどのようなものでしょうか。この問に対する答えは一朝一夕には出すことができません。エコツーリズムの歴史はまだ浅く、未だ多様に解釈され明確な定義が定まっていないからです。 「エコツーリズム」という言葉は「エコロジー」と「ツーリズム」の造語であるというのは想像に難くないため、この言葉を見聞きしてまず想像するのは、なんらかの「自然と親しむ」旅行であるというものでしょう。実際一般的にエコツーリズムというとこう解釈されることが多いです。我々が普段耳にする「エコロジー」という語は、このような「自然環境に優しい」という意味合いのみが強調されて使われることが多いですが、実際には「ecology」は「生態学」とも訳されます。「生態学」とは簡単にいうならば「生物の生活に関する科学」であり、自然と共生している人々の活動を含めた、生態的要素すべてを扱っています。 この「エコツーリズム」における「エコロジー」は後者の訳として使われており、故にエコツーリズムが扱うのは「自然とのふれあい」と「地域の人間とのふれあい」です。「自然散策やアウトドア志向型の観光ならこのようにエコツーリズムが叫ばれ始める以前からあったではないか」、と思う人も多いかもしれません。しかしこれまでの観光は資源を限りなくオーバーユースし、いずれは回復も困難になり結局は自然や伝統文化の破壊者となってしまうようなものでありました。これに対しエコツーリズムは、簡単に表現するなら「地域の環境や生活文化を破壊せずに自然や文化に触れ、それらを学ぶことを目的とする旅行」であるといえます。 エコツーリズムの3つの目的
第二に、「地域固有の資源を生かした観光の成立」。マスツーリズムにおける観光開発においては、対象となる地域の外部にある企業や団体が開発主体になる、いわゆる「外発的観光開発」が圧倒的に多かったため、利潤の追求のみを目的として地域社会の意向が軽視されたり資源に関する知識不足から資源の破壊などがしばしばおこりました。これに対しエコツーリズムにおいては、地域固有の自然環境や文化遺産などの資源を維持可能な形でフルに活用した観光開発を行うにあたり、それらの資源に最も関わりの深い人々、資源に関する知識を最ももっておりエコツーリズムによる利益や害を直接うける人々が主体となって行う「内発的観光発展」が原則となります。 そして第三に、「地域経済の活性化」があげられています。これはエコツーリズムのもっとも重要な要素といえるかもしれません。これまでのマスツーリズムにおいてはツーリズムにおける収入のほとんどは観光業者が得るものであり、それゆえに利潤のみを追求した、その地域の自然環境や生活を考慮しない観光開発が行われ、結果自然や文化遺産、現地の人々の生活環境は劣化の一途をたどるばかりでした。エコツーリズムにおいては、ツーリズムによる収入が現地の自然環境や文化遺産の保全のために使われ、かつ雇用機会の増大などにより現地の住民の利益になることが鉄則であるとされています。 |